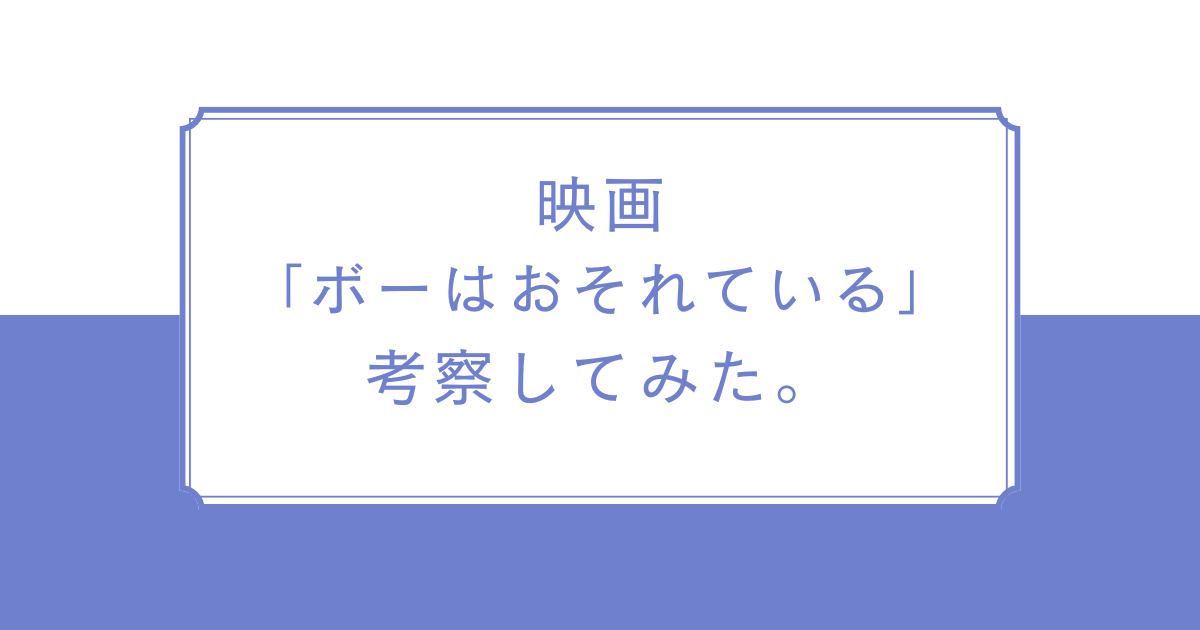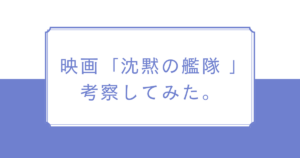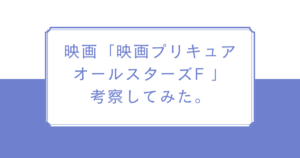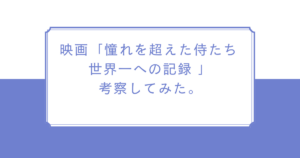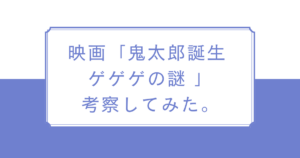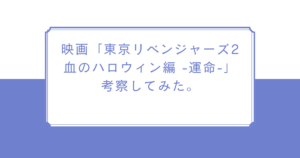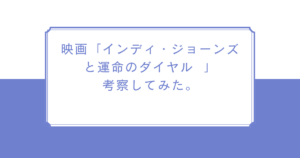アリアスター監督の最新作「ボーはおそれている」は、その衝撃的な内容と重厚なテーマ性で多くの映画ファンを驚かせました。
主人公ボーの視点を通じて描かれるシュールで不条理な世界は、観客に強い印象を与え、議論を呼んでいます。
この記事では、映画の重要なテーマや象徴について考察し、物語の奥深さに迫ります。
考察①母親モナの支配と運命論
物語の核となるのは、主人公ボーに対する母親モナの絶対的な支配です。
彼女は自らの愛を過剰に注ぐ一方で、それが返ってこないことに不満を抱き、息子を完全に支配しようとします。
モナはボーに嘘をつき、父親や祖父もエクスタシーに至った瞬間に死んだと信じ込ませます。
この嘘によって、ボーは生涯にわたり性的にも精神的にも自由を奪われます。
物語は、ボーがモナの作り上げた世界の中で試される構造になっています。
これは、映画全体が「母親によるトゥルーマンショー」のようであり、ボーは最初から最後まで運命によって操られる存在として描かれています。
また、アリアスター監督の他の作品と同様に、冒頭から結末までが繋がる構成が特徴的です。
産道から始まり産道で終わる本作は、ボーの人生が最初から母親の手の中にあったことを象徴しています。
考察②カタルシスの不在と絶望の反復
「ボーはおそれている」は、徹底的にカタルシスを打ち壊す構造になっています。 一見、観客に満足感を与えそうなシーンも、すぐに絶望へと反転する展開が続きます。
たとえば、ボーが劇中で理想の人生を夢想する場面では、一瞬の希望が描かれます。
しかし、その直後、現実の厳しさに引き戻され、観客もボーとともに絶望感を味わいます。
同様に、ボーが初恋の人エレインと再会し、性的な自由を手に入れる瞬間も描かれますが、それも悲劇で終わります。
このように、本作はカタルシスと絶望を繰り返すことで、観客に深い無力感を与える映画となっています。
映画のラストでは、ボーがついに母親モナに逆らい海へ漕ぎ出す場面があります。
しかし、それさえもモナによる裁きの場へと繋がり、ボーは完全に運命に屈する形で物語が終わります。
考察③フィクションと現実の境界
本作では、フィクションと現実の曖昧さが強調されています。 ボーの冒険は、彼の不安症やトラウマが生み出した妄想と現実が入り混じったものであり、その境界は観客にも明確には提示されません。
たとえば、劇中劇のシーンでは、ボーが理想の自分を投影する一方で、それが現実とどう繋がるのかは明らかにされません。
この曖昧さは、映画そのものが持つ「フィクションの意味」を問いかける意図があると考えられます。
また、ボーのセラピストが実は母親と繋がっていたという展開や、観客自身が劇中に登場してボーの審判を見届けるメタ的な描写も、フィクションと現実の境界をぼかす仕掛けです。
これにより、映画は観客にとっての「物語」の役割を再考させるものとなっています。
まとめ
「ボーはおそれている」は、母親モナの支配とボーの無力感を通じて、運命論や人間の自由の問題を深く掘り下げた作品です。
カタルシスを意図的に拒む構造や、フィクションと現実の境界を曖昧にする演出によって、観客に強烈な印象を与えます。
この映画は、ただのホラー映画にとどまらず、アリアスター監督自身の創作意図やトラウマを反映したメタ的なコメディでもあると言えるでしょう。見る人によって解釈が分かれる奥深い作品であり、一度では理解しきれない余地を残した映画です。
再鑑賞を通じて、新たな気づきを得られる作品として、多くの議論を呼ぶことでしょう。